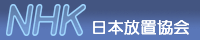手術前日20:00から絶食開始。前日24:00から絶飲開始、水一滴も飲めません。
因みに手術は夕方の予定。看護師さんの管理の都合上、手術時間に依らず一律で絶飲絶食の時間を管理してるそうな。
さて、半日耐えられるのか?と思ってたら、朝から早々に点滴開始。すると、空腹感もないし喉も乾かない。点滴すげぇよ!
そんなことを思いながら、同室の人が先に一人、また一人と手術室へ向かい消えていく。二人とも午前中に手術室へ向かったのに、昼下がりになっても一向に帰ってこない。
とうとうウチの予定時間になっても二人は帰ってこないし、ウチも呼ばれることがない。予想通り遅れてそう。
ようやくウチが呼ばれたのは予定時間を1時間以上回った頃。術後に晩飯が出るって聞いているけれど、晩飯は何時になるんだ?