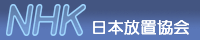胃カメラキメてきました。いやね、去年の人間ドックのバリウム検査(胃透視)で「ポリープあり」なんて言われたもんでね。その後、精密検査も再検査も言われなかったんでたぶん良性ポリープだったんだろう・・・と自己解釈してました。
ただ、今年は流石にちゃんと見た方がいいだろうと。でも胃カメラってしんどいって聞くし、どうせなら鎮静剤ありのところを・・・と探してみると、鼻から突っ込む胃カメラなんてものを見つけた。なんでも負担が少ないとか。よしこれだ!
申し込みの時から「鎮静剤ありで!」「鼻からで!」と伝えるも、受付の人も案内の人もなんとなく言葉を濁すだけでなんなんだろうなーと思ってたら、鼻からの時は鎮静剤使わない(要らない)とのこと。検査直前の説明で初めて知ったよ・・・。みんな教えてよ・・・。
そいで検査開始。まず鼻からカメラの通りをよくする薬が入れられる。「喉まできたら『飲んで』ください」。お、おぅ。これは余裕。鼻から液入れて飲むとか、ちょっとインドの修行僧な気分。
次に麻酔のゼリーが鼻から注入される。甘いストロベリー風味。鼻の奥に達するやいなや「痛い・・痛い・・・痛い痛い痛い痛い!」麻酔が鼻の奥の粘膜を刺激して痛いのなんの。まぁ、10数秒もしたら麻酔の効力が優ってきて痛みは引きました。
次にルアーの擬似餌のワームみたいな柔らかいチューブを鼻に突っ込まれる。鼻の通りを確認するも、どうも鼻の穴が狭いらしい。左の穴でギリ通る。
そしていよいよ本番、鼻カメラ(経鼻内視鏡)、鼻から挿入するも鼻の奥(一番狭いところ)でつっかえる。ゆっくりと挿入するも「痛い・・・ちょい痛いです・・・」。先生がここで「んー無理かなぁ・・5分くらい頑張れる?」と聞かれる。
最初の説明で、鼻が通らなかった場合は胃カメラに変更すると聞いていました。それは避けたい、何としても避けたい。「多分、大丈夫です!いけます!」そのまま少し無理して狭いところをカメラが押し通ると、通って仕舞えば後は痛みもなく余裕でした。
先生と会話しながら自分の胃の中をカメラで見せられ「十二指腸がちょっと赤いなぁ・・・お酒飲むの?」「はい」「じゃぁ控えようねぇ」「はい(今晩、呑み会だけど)」なんて感じで検査はサクッと終了。ポリープどこやねん?ってくらい異常なしでした。
そしてここからが地獄の始まり。
検査後は、最初は麻酔の影響で鼻の奥がなんか変・・・くらいだったのが、次第に麻酔開始時の鼻の奥に麻酔が染みる痛みが、だんだんと強く。さらにカメラを通した左の鼻の奥がヒリヒリ痛み出す。
1時間くらいしたら水飲んでくださいね・・・と言われるも、1時間経過後くらいがピーク。プールや海で鼻から思いっきり水吸い込んで、鼻の奥が痛くなる感覚の5倍マシくらいの状態がずーーーーーーと続く。マジで涙が出るくらい。
1時間経過以降から、喉に垂れてくる鼻水の味がストロベリー味に。おまえ!まだおったんか!今頃になって注入した麻酔が鼻水で流れ始める。そして鼻の奥の痛みに追い打ち。
検査終わって電車乗って会社行ったけど、移動中の電車の中で上向いて目を瞑ったまま泣いてました。(上向かないと鼻水が垂れるから)
2時間経過してようやく、耐え難い痛みから普通の痛みに。晩には痛みほとんどなくなったけど違和感は翌日まで続きました。
もう2度とやらねえよ・・・。
(個人差があります)