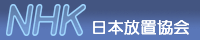前々から気になっていたLCのフォークオイルを変えることに。まだ6,000kmほどで激しく走っているわけでも無く、交換時期にはまだ早い。しかし、とにかくフロントの動きがいまいち。なんというかがさつ。ハスクと比較したら、なんだこれ?減衰がほとんど効いていなくてスカスカ…。オーナーマニュアル指定ではSAE 2.5W(約15cSt?)というシャバシャバの倒立用オイルだけど、もっと堅めのオイルに変更してみた。
LCのFフォークは見た目倒立なんだけど調整機構が無くて、やや「なんちゃって倒立フォーク」。しかもスプリングは右側だけ。某所で「右側がバネと圧縮側減衰で、左側が伸側減衰のみ、左右でオイル変えると圧/伸で調整できるかもね♪」なんて情報があったけど、左側を手で動かしてみた限りでは圧側も少し減衰力があるので、完全に分離してはいない模様。右側はスプリングが堅すぎてよく分からなかったです。
ちなみにオイル量の情報が無い。油面計ろうにも、0Gの状態で油面はピストンバルブよりも下にあるんで見えないし。油面低すぎ?結局抜いたオイルをメスシリンダーで実測してみたところ、だいたい右360cc/左250cc。抜いたオイルは綺麗に透き通ってました。10,000kmぐらいで抜いたときに、すでにスラッジでドロドロだったKLX125とは大違い。
とりあえず左にカヤバG10S(41cSt)、右にカヤバG15S(55cSt)を入れてみる。時間が無くてオンロードしか走ってないけど、2.5Wからなんでやりすぎたか?と思ったものの割と違和感無い。ただ、少し硬すぎるような気もしたんで右もG10Sに入れ替えたところ、割としっくり…でもちょっと柔らかい?これ以上の調整は山かコース走ってから考えるかな。少なくとも初期の2.5Wよりかなりいい感じに。
んで、ふと2016年のパーツリスト見たら、指定オイルがいきなり2.5Wから15Wになってるし。やっぱりユルかったんだよね?
ちなみに、うちのは2015モデルでFフォークがOlle amortidors製だけど、2013まではPaioli mechanica製なのでまた話は違ってくると思われます。片側スプリングの構造はどちらも同じだけれども、パーツリスト見ている限りだいぶ構造違うみたい。イメージ的にはPaioliのほうが大手だし、ヤマハとカヤバの資本入ってるし、そっちのほうが良かったなぁ…。
追記:つづく
-
最近の投稿
- 交渉 2025年8月31日
- とある蕎麦屋さん 2025年7月28日
- Bambu lab P1Sはいいぞ 2025年7月21日
最近のコメント
- Starlink miniで遊んでみた に 棉乃木 より
- Starlink miniで遊んでみた に SHIU より
- Starlink miniで遊んでみた に 匿名 より
メニュー
タグ
- computer (141)
- es (1)
- FreeBSD (48)
- KLX125 (109)
- music (20)
- N-VAN (9)
- RR4T 125LC (33)
- RR50 Factory (6)
- server (104)
- Sur-ron (5)
- TE250(4st 2010) (55)
- TE250i (12)
- UltraBee (2)
- ZX6R (28)
- ZXR400 (14)
- お父さん (8)
- アニメ老人会 (1)
- エンデューロ (4)
- コミック (92)
- モーターサイクル (170)
- レース活動 (27)
- 人指し指縫合 (9)
- 初めての入院と手術 (15)
- 園芸 (35)
- 怪我 (12)
- 旅行 (125)
- 燃料電池 (4)
- 脊椎圧迫骨折 (3)
- 腓骨筋腱脱臼 (9)
- 自動車 (43)
- 道具 (59)
- 酒 (55)
- 鎖骨骨折 (2)
- 靱帯損傷 (6)
2025年9月 月 火 水 木 金 土 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 アーカイブ
メタ情報
- 2002年11月以前の日記(tDiary移行前)はこちら