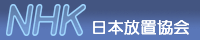2stとはなんぞや
 2ストローク機関(wikipediaより)
2ストローク機関(wikipediaより)
一般的には「2工程で1周期とするエンジン」「1回転毎に1回爆発するエンジン」と言われるけれど,その仕組みを理解するにあたりずーっとピンと来なかった。記事を書くにあたり,改めて2stの仕組みを調べていくと,別の視点のほうが自分としてはしっくりきました。
それは「吸気・掃気を下死点で一度に行うエンジン」という特徴。
通常の2stでは,ピストン下降を吸気の予備圧縮に利用しているけれど,現状実用として残っている数少ない2stエンジンであるユニフローディーゼルに至っては,外部の過給器圧力で新気を送り,ピストンはただ圧縮・爆発の為だけで吸気掃気には関与していない。
 ユニフローディーゼル(wikipediaより)
ユニフローディーゼル(wikipediaより)
そして,そのように2stを理解すると,ユニフローディーゼルのほうが2stとしては有るべき姿で,クランクで予備圧縮を行う一般的な2stは,外部の過給器を簡略化した簡易版の様に見えてくる。
それもそのはず,2stの歴史をひもとくと,初期のクラーク式では吸気を圧縮する為のシリンダーを別に1気筒用意し,その圧力によって吸気掃気を行っていたという。
 クラークのエンジンに類似した機構(wikipediaより)
クラークのエンジンに類似した機構(wikipediaより)
やはり2stでは,下死点で吸気掃気を一度に行う為に,シリンダー外で十分な負圧・正圧が必要ということが分かる。そして,それこそが2stたる所以だと思う。
クランクによる混合気予備圧縮の功罪
4stのような複雑なバルブ機構を持たず,4stと比較して排気量あたりの出力が高い2stは,その小型・高出力から特にオートバイにうってつけのエンジンだったことは敢えて言うまでも無い。
吸気掃気の圧力をクランク内圧を使って行う事により,外部補機を極力廃して小型・簡素化を実現した2st。
しかしその仕組みから,排ガス規制をクリアすることが難しかった。その理由は下記の通り。
- 吸気の生ガスの一部が,掃気側へ抜けてしまう。
- 予備圧縮時にクランク内に混合気の一部のガソリンが滞留する為,空燃比が安定しない。
※2は,ユニフローディーゼルでは外部過給器により解決されている。
2は特に重要で,空燃比をリーンバーンに制御が出来ないと排気温度を上げる事が出来ないので,3元触媒が使えず今時の排ガス対策が全く成り立たない。また,2stのプラグがかぶりやすい原因も,クランク内に滞留するガソリンによる物と言われている。
クランク内は,気化前の液体のガソリンや滞留したままの混合気で満たされていて,直接制御の出来ない第二のキャブレターみたいなことになっています。ストップ&ゴーでクランクのガソリンは濃くなり,連続走行では薄くなっていきます。
2stのインジェクション化が難しかったのも,混合気がクランクを経由することが要因と思われ,クランク内に滞留する残留ガソリンの予測が付かず,インジェクション化してエンジンが動いても,空燃比の制御が出来ないのならキャブに対するメリットが殆ど無かったんじゃ無いかと思います。
ホンダの考え
実は2015頃にホンダの2stインジェクションに関する特許が少し話題に上がっていました。

内容としては,ざっくり言うと,ユニフロー化(シリンダー上部に排気バルブ)しつつ,過給器ではなくクランクによる予備圧縮で空気のみ圧縮し,ガソリンはシリンダー内へ直噴,直噴化したユニフローディーゼルに,プラグ付けてディーゼルじゃなくして過給器も外しました,みたいな内容。
実際に開発してるかどうかは中の人のみぞ知るですが,混合気がクランクを通らないため,ユニフローディーゼル同様に排ガス問題は改善出来そうです。
実はこれ、4輪メーカーも同じ様な事を考えていて、既に2000年前後には諦められてしまった技術のようです。
ユニフロースカベンジング式2ストロークガソリン直噴エンジンの可能性(wikipedia)
シリンダー内への直噴インジェクターが4輪で実用化されているとはいえ課題もあり,まだまだ発展途上でありネックかもしれません。
また,排気バルブ機構が必要な為,エンジンが4stなみに複雑・大型化するため,排気量あたりのパフォーマンス追求ならまだしも,そうでなければ4stと総合的に比較してメリットあるのか?判断が難しいところかと思います。
KTMの答え
ここで満を持して登場したKTMの2stインジェクション。
 Motocross Action Magazine より
Motocross Action Magazine より
もっと簡単に「掃気ポートに対して燃料噴射する」という解決策を取っています。
混合気がクランクを通らないので正確な空燃比の制御が可能になるかと思います。また,正確な空燃比制御が出来るという事は,2st特有のプラグのカブリからも開放されるんではないかと思います。
掃気ポートへの噴射自体は,結構古くから有るアイデアのようで80年代後半の特許( EP0302045B1)や,2000年頃にはその改良特許なんかも見つかります。US6691649 B2
その頃日本メーカーはというと,残念ながら2stを捨てて4stに舵を切り始めたばかり…。
吸気掃気時に生ガスが排気側に洩れてしまう点について根本解決は出来てませんが,空燃比制御でリーンバーンが出来ると三元触媒が使えますし,ひょっとしたらインジェクターの噴射タイミングを僅かに遅らせて,排気側へ洩れる生ガスを減らしているのかも知れません。
そんなわけで,掃気ポート噴射=Transfer Port Injection(TPI)というのは,絶妙な解決策の様に見えます。
むしろ,キャブレターだって掃気ポートに付けるべきだったのでは?と思えるくらいです。(それはそれで大変だけれども…)
ただ、2stTPIと言えども、シリンダー内の燃焼済みガス交換の不完全さと、生ガスの吹き抜けの課題は抱えたまま。他の用途では「燃費・排ガス」の優先順位が高い為、TPIは将来的にもエンデューロだけのニッチなままかな…という気はします。