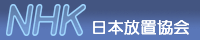もともとは「山廃仕込みとはなんぞや?」と調べ始めたのが発端。
日本酒の造り方(酒母の作り方)には、大別して生酛/山廃/速醸とあります。元々は生酛からはじまって、山廃、速醸と少しづつ工程を簡略化していった技術進化の過程となっています。
今では多くの日本酒が速醸で造られているので、多くの解説文章では、まず最初に速醸の作り方を説明してから生酛の説明に飛んで、次に山廃の説明となり、順序がちぐはぐになってます。
また、淡々と行程を説明した物が多く「何故その行程が必要なのか?」が、かなりアバウトにしかなかったりします。いやまぁ、説明し出すと切りが無いわけですが。
山廃仕込みがなんぞや?って言うのが、ちょっと頭の中で整理できたのでその備忘録。
もくじ
日本酒の仕込みと酒母(酛)について

ごく簡単に日本酒の造り方を説明すると「米と麹菌と酵母菌を使って造ります」となります。
ただいきなり米に麹菌と酵母菌をぶち込むんでは無くて、まずそれぞれを少量の米を使い一定の管理下に置きながら、それぞれ麹菌と酵母菌を増やしていきます。
十分にそれぞれの菌が増えたところで、大きなタンクで大量の米と混ぜて日本酒の発酵を進めていきます。
麹米の作り方・混ぜ合わせた後の発酵過程について、それぞれ書き出すと長分記事二本書けてしまうと思いますがここでは割愛。
生酛/山廃/速醸の違いに直接関係する、酵母菌を増やす酒母(酛)の作り方について書いて行きたいと思います。
酒母の作り方の違いこそが生酛/山廃/速醸の違いなんですが、まずは古来から有る生酛の作り方を基本として以下説明していこうと思います。
生酛造りの酒母造り
麹菌による米の糖化と酵母菌によるアルコール発酵
ごくごくざっくりした日本酒の発酵過程の説明ならこれで終わり。米のデンプンを麹菌が分解して糖にして、その糖を餌にして酵母菌がアルコールを造ります。
じゃぁ、米に麹菌と酵母菌をぶち込んだら日本酒が出来るか?というと出来ません。まぁアルコールを含む「何か」は出来るかもしれませんが、不味くて飲めたもんじゃ無い…と言うか下手したら腹壊すかも。
と言うのも、発酵と腐敗は表裏一体なんで、発酵が進む条件=腐敗が進む条件でもあります。発酵食品というのは「意図する菌種」だけを育てて「意図しない菌種(雑菌)を防ぐ」事が必要なので、製造工程は常に雑菌との戦いです。
ではどうやって麹菌と酵母菌だけが育つ環境を整えているのかというのが、次の(一つ前の)ステップ。
乳酸菌を使って乳酸を生成して殺菌する
食品殺菌の一つの方法に「食べられる酸」を使うというのがあります。食酢もその一つです。ただ食酢は日本酒(アルコール)から造られるのですが、それよりももっと単純に糖から造れるのが「乳酸」。ヨーグルトとかの酸っぱい成分です。
乳酸菌を使って十分に酸度のあがった環境下にして他の不要な雑菌を殺し、ようやく酵母菌が活動を始める環境が整います。酵母菌にも色々あるのですが、乳酸に対して強い耐性を持つ酵母菌が日本酒には良い菌とされています。
酵母菌というのは環境中にも様々な種類が居て「野生酵母」なんて呼ばれていますが、多くの場合はそれらの野生酵母が無秩序に育ってしまうと酒の味は不味くなり「腐造」という状態に。そいつらは酸に弱いので、そいつらを淘汰するためにも乳酸が必要です。
そして頑張って乳酸を造ってくれた乳酸菌ですが、乳酸が一定上の濃度に達すると自身の乳酸に耐えきれず弱ってゆき、さらには酵母菌がアルコール発酵を始めるとアルコールにも耐えきられず、十分に酒母のアルコール濃度が上がった頃にはすっかり死滅します。おかげで必要以上の乳酸発酵は、ここで停めることが出来ます。
このときに、まれにアルコール耐性のある乳酸菌が生き残ってしまい、いつまでも乳酸発酵が続いてしまう事があります。その場合、出来上がった酒の味はとても酸っぱく飲めたもんじゃ無くなってしまいます。これを「火落ち」と呼び、一度発生すると器具を洗浄しても何度も繰り返し発生するようになり、蔵としてはたまったもんじゃ無いそうで・・・。
ただ、乳酸菌を増やす過程というのも、他の雑菌が繁殖しやすい環境です。乳酸菌が増える前に雑菌が増えてしまうと、乳酸が増える前に乳酸菌自体が他の雑菌に負けて数が増えなくなってしまいます。
なんだかマトリョーシカみたいになってきましたが「雑菌を抑える為の乳酸菌の雑菌を抑える」事が必要で、それがさらに次の(前の)ステップ。
硝酸還元菌を使って亜硝酸を生成して殺菌する
酒母造りを調べ始めて初めて知ったのですが、ここで硝酸還元菌が活躍します。井戸水や湧水には、硝酸還元菌や硝酸カリウム(硝石)が含まれています。その名の通り硝酸塩を還元して、亜硝酸を生成、これが殺菌作用を持つので十分に亜硝酸を増やして乳酸発酵前/発酵中に他の雑菌を抑えます。
ここで乳酸菌や酵母菌の発酵過程と違うのは、この行程では5˚Cくらいの非常に低い温度を保ちます。そうすることで、亜硝酸の濃度が上がる前に他の雑菌が繁殖することを抑えるそうです。硝酸還元菌達は比較的低い温度にも適応するようです。
乳酸菌→酵母菌の時に乳酸菌が死滅するのと同じように、乳酸菌による乳酸濃度が上がると硝酸還元菌達は急速に死んでいきます。生成された亜硝酸も基本的には毒物ですが、不安定な物質故に時間と共に分解されて、酛が出来上がる頃にはすっかり消滅しています。
硝酸還元菌について
「硝酸還元菌」というのは主に日本酒界隈で利用されている言葉のようで、特定の菌種を指すわけでは無い様です。自然界の土壌や淡水・海水に広く分布する好気性(酸素を好む)の菌類の多くが、酸欠状態になると酸素の代わりにと硝酸還元能力を持っているようです。
硝酸還元菌については、以下のブログにとても興味深い事が書いてありました。
面白いのが、硝酸還元菌とは、ぶっちゃけ風呂場のヌルヌルとか日和見感染すると大変な緑膿菌とか「不衛生なばい菌」の代表格みたいなやつらが日本酒造りに役立ってます。
勿論量が多すぎたら人体に害をなすんでしょうが、逆に一切菌類のいない綺麗な水だと、酒造りの過程で他の雑菌がのさばってしまい腐ってしまうというのが、とても面白いです。よくもまぁこんな方法を見出したもんです。
そんなわけで生酛のまとめ

https://www.sbj.or.jp/wp-content/uploads/file/sbj/9612/9612_yomoyama.pdf
今まで説明してきたとおり、本来の酒造りに必要な酵母菌こそが「清酒酵母」と呼ばれる物で、それらの発酵を行うまでに野生酵母をいかに淘汰するか、というのを図に表したのが上記の図です。
今では清酒酵母は、純粋培養した物が用いられるのが主流(乳酸菌も含め)ですが、日本古来の日本酒造りでは、すべて空気中に生きている野生酵母達の中から必要な酵母だけをより抜いて発酵させていました。
では山廃とは?
ようやく冒頭の「山廃とは」という話になります。一番簡単な説明としては「山卸し」行程を省略しました、です。山卸しの作業自体は他のサイトに詳しく書いてあるのでそちらを見て下さい。
「山卸し」の行程では、一般的には「後の行程で発酵が進むように米をすりつぶす作業」とされ、「今ではしなくても酒の味に違いは無かったから廃止した」とだけあっさり書かれていたりします。
じゃぁ、山卸し自体ほんとに必要の無い行程でただ無くしただけだったか?というとそうでは無いようです。主に、山卸しを省略できるようになった理由は以下の3つがあります。
- 山卸しをしない代わりに水麹を使って「櫂入れ/汲掛け」を行う
- 精米機の普及により精米歩合の進んだ米を扱う
- 硝酸カリウムの添加
山卸しでは雑菌が繁殖しない様にと、低い温度でかつ水分量を減らした粘土みたいな米の塊を櫂ですりつぶす重労働でした。しかし、麹米を水で溶いてその状態で十分に麹菌を繁殖させた水麹と混ぜ合わせる(櫂入れ/汲掛け)ことにより、麹菌の酵素の力で米が十分に溶ける(分解される)ことが分かりました。櫂入れ/汲掛けは山卸しよりは随分と楽な作業になりましたが、ただ山卸しを無くして何もしなかったわけでは無かったようです。
そして、精米機が普及することにより精米が簡単にできるようになり、脂質を多く含み溶けにくい米粒の外側部分が減りました。そして、より麹菌の酵素により米が溶けやすくなります。
ただそれだけだと、蔵によっては山廃で仕込むと亜硝酸による殺菌力が不足して腐造になってしまうことが有ったようです(意図しない野生酵母の繁殖による「早沸き」)。
先に述べた、硝酸還元菌を育てる過程ですが、一般的には乳酸菌が働き出す前段階の「打瀬」という工程で増やすと言われてます。山卸しはその打瀬よりも前の工程ですが、山卸しの有無によって硝酸還元菌の働きに影響があったようです。
そして、その働きを補ったのが「硝酸カリウムの添加」。
硝酸カリウム添加
硝酸カリウムの添加は山廃に限ったことでは無く、本来の生酛についても蔵によっては行われています。そもそもは明治後期頃からの国立醸造試験所の指導です。
灘の宮水や西条のような酒所の仕込み水には、元々硝酸カリウムの含有量が多いことにより他の地域よりも腐造のリスクが少なかったことがわかり、腐造を避けるために他の地域では硝酸カリウムを添加する事が推奨されました。
添加物ということで、結果よりも建前が気になり敢えて添加を避けている蔵も少なくないようですが、それでも山廃は宮水でも無ければ添加なしには難しいようです。
そして速醸とは?
日本酒造りの進化の最終形態?今時の日本酒の殆どが速醸です。
酵母菌の増殖に乳酸が必要で、今まではそのために雑菌が入らないよう、色々と工夫して行程を積み重ねていましたが「だったら工業的に製造した乳酸を最初から投入すればいいんじゃね?」って言うのが速醸。そもそも乳酸発酵の過程がありません。
酵母菌も純粋培養したモノが用いられます。現在流通している日本酒のほとんどがこれ。
「行程が簡略化された=単調な味」とも限りません。よくある地酒の良い香り「吟醸香」は酵母菌によって造られます。また、糖分やアミノ酸は麹菌と酵母菌によるものです。
純粋培養した酵母菌を使っていると言っても、どうしても天然酵母も紛れ込んでしまうそうで、それらは酒の味を良くも悪くもしながら、個性的な味を醸し出しています。
生酛/山廃/速醸の関係

こうしてみると、生酛/山廃が速醸とは分けて「生酛系」と分類される理由が良く分かります。速醸系との違いは、乳酸発酵を経て乳酸を得るかどうかが大きな違いです。
硝酸カリウムの添加については「宮水以外の山廃では必須」というのが主流のようですが、添加せずに山廃を造っている蔵もあれば、腐造を防ぐために生酛ながら添加している蔵もあり様々です。
また、古来の「生酛造り」とは、乳酸菌も酵母菌も空気中やその蔵に多く住み着いている菌種(蔵付き酵母と言われる)を使い、米と麹菌以外は添加しないものですが、今では乳酸菌も酵母菌も純粋培養した物を使う方法もありますし、硝酸還元菌ですら純粋培養したものがあります。良い悪いかは別として色々です。
味の方はというと、多くの人は速醸系と生酛系(生酛/山廃)の違いは一口で分かると思います。速醸系に対して生酛系は「しっかりした味」の物が多いです(合わない人にとっては癖のある味)。一部、速醸ながら「しっかりした味」なんてのも有ったりするので一概には言えないのですが…。
では生酛と山廃での味の違いは?と言うと、正直私には分かりません。生酛か山廃か、と言う差異よりも、蔵ごとの違いの方が大きいと思います。
「生酛なら硝酸カリウム添加してないから、僅かながらの雑菌の繁殖で複雑な味になるのでは?」とか「いやいや山廃で硝酸カリウム添加していない蔵の方がもっと野性味溢れる味かも?」など、色々推測はできますが、そもそも生酛も山廃も、今では添加の有無、純粋培養酵母の利用の有無など、千差万別です。
結局の所は「呑んでみないと分からない」というのが正解。つまりはただの蘊蓄でしかないんですけどね。
参考サイト:
- 日本釀造協會雜誌 「清酒醸造100問100答」1965
- 外池良三/国 税庁醸造試験所「醸造家のための微生物の話6」1965
- 一般財団法人環境イノベーション情報機構 Q&A「硝酸塩還元菌について」2003-06-26
- 西尾 昭・茂 一孝「乳酸菌と硝酸還元菌の添加による生もと系酒母製造の安定化」2008
- 新政酒造 蔵元駄文「I LOVE 硝酸還元菌!!」2010-10-3
- 新政酒造 蔵元駄文 「乳酸菌というもの2」2012-06-01
- 南部酒造場 花垣 「【蔵】生もと もと摺り」2014-01-06
- SAKETIMES 「山廃酛や速醸酛の誕生に貢献!明治時代の政策が現代の酒造りにもたらしたもの」2017-03-08
- 日本生物工学会 「続・生物工学基礎講座バイオよもやま話『生酛の歴史と未来』」2018
- SAKETIMES 「酒母をつくるのは強い酵母を育てるため─「速醸系酒母」と「生酛系酒母」の製法を比べてみた」2021-03-05
- 地酒とワインの店 濱田屋 「雑菌との闘い~日本酒編~」
- 板倉酒造 天穏 「無添加 生もと・山廃仕込み」