ちょっとした興味本位で和食におけるスパイスってどれだけあるだろう?って調べてました。ざっくりイメージする和食って,西欧や中華みたいにガツガツスパイス使わないからあんまり無いんじゃ無い?って思ってましたが,意外に少なくありませんでした。
所謂「和食」というのは,その殆どが江戸時代に基礎が築かれたり発展していて,主に17~19世紀あたりを中心につらつらと調べてます。
和食の香辛料に依ると「唐辛子,山椒,山葵,紫蘇,大葉,荏胡麻,胡麻,蓼,柚子,芥子,麻の実」など。わりと少なくは無い?ただこの記事には記載ありませんが,他にも江戸時代頃には既に「胡椒」が使われていたようです。それも高級品としてでは無く,うどんに掛けたりごはんに掛けたりという,大衆的な使い方として。
その根拠については,
- 江戸時代の浄瑠璃/歌舞伎の台詞で,うどんに胡椒を掛ける台詞がある。
- 江戸時代の料理本「名飯部類(めいはんぶるい)/享和二年(1802)」に「胡椒飯」の記載がある。
- 古典落語の「くしゃみ講釈」で,胡椒と唐辛子を取り違える話がある。
大航海時代には「金と同じ価格で取引されていた」なんて逸話のある胡椒ですが,その根拠となる文献などはざっと見た所見つかってない様です。一方で胡椒の値段にて胡椒の価値を文献から検証していて,それによると16世紀後半のイギリスで金1g=胡椒236g,最も高かった?13世紀フランスでも金1g=胡椒72g程度で,確かに高価ですがそれほどでも無かったようです。
一方で日本の場合は,16世紀の長崎貿易の記録によると金1g=胡椒3600g。これは現代の胡椒市販価格よりもさらに安い。その理由については胡椒~その2 | Falx blog 2に依ると,インドまで行かなくても中国南方産の胡椒が比較的安価に手に入った可能性が指摘されてます。西欧のように「ペストの特効薬」という見方も無かった為,そもそも東方ではあまり高騰しなかったようです。
そんなわけで,江戸時代頃から日本人にとっては手軽な調味料であった胡椒ですが,残念ながら和食で利用される機会も少なく,うどんも最初は胡椒が定番だった物が,やがて一味/七味唐辛子に置き換わって行ったようです。その後,明治維新を経て再び肉食文化が浸透するに従って,再び胡椒が日本の食文化に登場するようになりましたが。
香りのある蕎麦に,香り控えめの唐辛子なのは分かりますが,元々香りの少ないうどんまで唐辛子になるとか,わりととばっちりのような気がします。今度うどんに胡椒を試してみようかと思います。

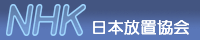
ピンバック: 辛いは旨い | 人生という名の酷道で遭難中