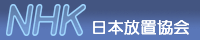調べてみたところ,EUの法令であるEU 168/2013を引用していてざっくり意訳すると以下の通り。(後ろの記号は,EUでのカテゴリ名。)
- エンデューロ二輪自動車(L3e-AxE[x=1~3])
- シート高 900mm以上
- 最低地上高 310mm以上
- 最も高いギアで最終減速比が6以上
- 装備重量140kg以下(EV/HVの場合はバッテリー含む)
- パッセンジャーの為のシートポジションが無いこと
- トライアル二輪自動車(L3e-AxT[x=1~3])
- シート高 700mm以下
- 最低地上高 280mm以上
- 燃料タンク4L以下
- 最も高いギアで最終減速比が7.5以上
- 装備重量100kg以下
- パッセンジャーの為のシートポジションが無いこと
国交省の発表資料では「オフロード競技用の二輪自動車。構造要件により規定。」としか書かれていなくて,肝心の構造要件が書かれていない。
一方で,法改正内容が載る官報(の写し)では「欧州連合規則168/2013に規定するエンデューロ二輪自動車及びトライアル二輪自動車を除く。」としっかりと要件が書かれている。
シートが高い高いと言われるWR250Rで895mmだから,普通の人が考える「オフロードバイク(KLX/CRF-L/WR-R/セロー)」は該当しないっぽい。実質的に外車の輸入用みたいな感じ?
因みに125LCさんはエンデューロ二輪自動車の規定満たしているっぽい(タンデムステップはどうなんだろう?)。
二輪ABSの機能オフスイッチ設置禁止規制と合わせて,上記競技車両を除いてオフロードバイクを撲滅しに来ている感じ。
「え〜,オフロードバイクって昔は公道走っても良かったの?,あれって競技専用じゃないの?」って言われる未来が近い。