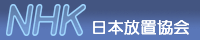古くからある芸能・技能や体術の手ほどきでは,殆どが最初に「型」から覚えさせられ,「理」は後から教えられる.
例えばプログラムという作業は,一見論理構造の地道な積み重ねのようで,実のところ覚えている「型」の組合せアレンジに思える.「経験の応用」は脳の働きとして「論理的思考」よりも得意としている働きだったと思う.
今日日の情報学科等の課程とかで,果たして「型」の習得に時間を掛けているのだろうか.ひととおりの制御構文や予約語の解説をしたら,いきなり例題に入ったりはしていないだろうか(それでも出来る人は出来てしまうんだけど…).プログラムという新しい分野に於いても,古典的な教導と同じく「型」の習得を重視するべきなんじゃないかと思う.
現実には学校教育という制度上,効率的に規定の学習時間内で規定の学習効果を上げなければならない.短期的に見れば「型」の習得に時間を割くことは非効率に見えてしまう.しかし「型」の習得を疎かにした結果が,使えないプログラマの量産であったり,使えない英語教育という結果を招いているように思える.
Webでたまたま見かけたソースコード見ながら「なんでこんな妙ちくりんなコード書くんだろう」とか思いながら….
-
最近の投稿
- 勇者刑に処す(アニメ)を観た 2026年1月19日
- マレット骨折(マレット指)と左手 2026年1月11日
- 英会話学習その後 2025年12月4日
最近のコメント
- マレット骨折(マレット指)と左手 に 棉乃木 より
- マレット骨折(マレット指)と左手 に ぷ より
- マレット骨折(マレット指)と左手 に 棉乃木 より
メニュー
タグ
- computer (141)
- es (1)
- FreeBSD (48)
- KLX125 (109)
- music (20)
- N-VAN (9)
- RR4T 125LC (33)
- RR50 Factory (6)
- server (104)
- Sur-ron (5)
- TE250(4st 2010) (55)
- TE250i (12)
- UltraBee (2)
- ZX6R (28)
- ZXR400 (14)
- お父さん (8)
- アニメ老人会 (1)
- エンデューロ (4)
- コミック (92)
- マレット指 (1)
- モーターサイクル (170)
- レース活動 (27)
- 人指し指縫合 (9)
- 初めての入院と手術 (15)
- 園芸 (35)
- 怪我 (26)
- 旅行 (125)
- 燃料電池 (4)
- 脊椎圧迫骨折 (3)
- 腓骨筋腱脱臼 (9)
- 自動車 (43)
- 道具 (60)
- 酒 (55)
- 鎖骨骨折 (2)
- 靱帯損傷 (6)
アーカイブ
メタ情報
- 2002年11月以前の日記(tDiary移行前)はこちら