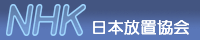そういうのがあるんだねー。最近付けてる人見るねー。知り合いがエンデューロレース前にいつも貼ってるねー。でも難しそうだねー、…位の感じで、特に注目はしていませんでした。
で、先日の「腓骨筋腱脱臼」の補助に関節固定のテーピング(キネシオテープではない)していて、それが割と良い感じだったので、じゃぁ巷で話題?のキネシオテープってどうなんだろう?と興味がわいた次第。
名称と商標について
キネシオロジーテープかと思ってたら、キネシオテープが本家?にとっては公式な名称のようで。「キネシオロジー」はもっと広い意味で、テープはその考えを生かした?というモノらしい。
そもそも「キネシオテープ」の呼称は本家?らしい特定団体が商標権握ってるんで、回避のために他のメーカーはキネシオロジーテープと読んでる事情もあるみたいで。
因みに、尼をちらっと検索してみたら普通のメーカー製のはみんな「キネシオロジーテープ」になってて、「キネシオテープ」を名乗ってるのはルール無用な中華ダイレクト製品ばかりという状態。
この状況って、商標権抑えている団体の望んだ結果では無いと思うんだけど…。
仕組み・理論について
で、キネシオテープがどう役に立つのか、いまいちどういう仕組みなのか分からない。関節固定用のテーピングは昔から有ったし良く分かる。
でもキネシオテープって、すごいゆるゆる。こんなんで、どう作用するの?と。で、困ったときのWikipediaさん。
健康な筋肉と同じ伸縮率を持つテープであるとされており、筋肉に沿って貼ることで効果を発揮するとされる。テープを張ることで体内に隙間が出来てリンパ液の流れが良くなり、それにより新陳代謝が改善し、自然治癒力が高まり、貼っておくだけで筋肉の痛みや凝り、怪我・手術後の内出血の治りが早くなると主張されている。
https://ja.wikipedia.org/wiki/キネシオテープ#概要
他の解説サイト見ても、だいたい同じ様なことが書いてありました。ただ、この時点で個人的にはもう眉唾なんですよ。そして、読み進めていると気になる記述が、
医学界からは、プラセボを超えるエビデンスはないと評価されている
因みに英語版のwikipediaでは、もっと痛烈に批判されていました。
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Elastic_therapeutic_tape?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ja&_x_tr_hl=ja&_x_tr_pto=wapp(googleによる日本語翻訳)
ちょっとググったところ、真面目に臨床試験とかやった結果もあり、一応は限定的な条件で限定的な効果はあったりするんですが、少なくとも、アスリートが日常的に使って負担軽減の効果があるような代物では無い感じでした。
理論についての疑念
そもそもキネシオテープってだいぶ弱い伸縮力(not伸縮率)なんですが、あの程度の引っ張りで体内に隙間が出来るとは思えないんですよね。
例えば、モトクロスやエンデューロライダー(ロードライダーも?)の間でよく知られている現象として「腕上がり(前腕コンパートメント症候群)」というのがあります。ある程度の運動量でまだ全然疲れてもいないのに指がマトモに動かなくなり、クラッチ/ブレーキ操作はおろかハンドルを握ることすらおぼつかなくなるというもの。
原因は、筋肉は筋膜という薄い膜に包まれているのですが、運動により膨張した前腕の筋肉が筋膜の伸縮限界以上に膨張し、結果として筋膜で締め付けられてしまうことがあり、前腕内の血管や神経が圧迫されて指の動きが阻害されると言われています。
実際に、腕上がり対策として「筋膜切開術」の手術を受けるライダーもいます。今では手術せずに筋膜を伸ばす為のトレーニング器具が有りますけど。
そんなわけで「日常生活」ではない「非日常」な競技レベルの世界では、それくらいパンパンに筋肉は腫れ上がっているので、皮膚の上から貼った弱いテープでちょっと引っ張ったくらいでどうにかなるとは思えないんです。
また、この「テープを張ることで体内に隙間が出来てリンパ液の流れが良くなり…」という働きそのものに関するエビデンスは存在しないようです。
いろいろな報告
医学界からは、プラセボを超えるエビデンスはないと評価されている。
医学のコミュニティと科学的懐疑主義のコミュニティは、キネシオテープには利点はあるが、プラセボを超える実証可能な科学的エビデンスはなく、疑似科学的治療であると明言した。
2012年に科学ジャーナリストの Brian Dunning は、オリンピック以外の場所でキネシオテープを付けた運動選手、プロビーチボールプレイヤーを見たことがない理由を熟考し、キネシオテープの人気は完全にテレビ放送のスポンサーをしていたためだと考えた。
https://ja.wikipedia.org/wiki/キネシオテープ
いくつかの先行研究から、負荷のかからない運動時には、キネシオテープを着用した方が疲労は少ないという結果が得られたが、負荷のかかる運動時にはテーピングの有無によって有意差は見られていないということが わかる。
http://www.waseda.jp/sports/supoka/research/sotsuron2006/1K03A095-8.pdf
[結論] KTは、肩の痛みのある患者にテープを貼った直後に、痛みのないアクティブROMを改善するのに役立つかもしれません。肩腱炎/インピンジメントが疑われる若い患者の疼痛強度または障害を減少させるためのKTの利用はサポートされていません。
https://bibgraph.hpcr.jp/abst/pubmed/18591761?click_by=p_ref
いちおう効果があったとされる報告もあるんですが、主にパフォーマンスが落ちている高齢者や障害者の運動補助、という側面が多いようです。
キネシオテープは貼付け部位及び方法に限らず、皮膚や筋腱等の皮下組織等の求心性入力を増加させ、身体の重心動揺を安定させる上で重要な因子である足関節のバランス能力を向上させたと言える。
そしてこれらの刺激は、加齢に伴うバランス能力の低下を防ぐ可能性があると考えている。
https://ousar.lib.okayama-u.ac.jp/files/public/1/10956/20160527184512877457/131_0051_0055.pdf
キネシオテープの脳卒中患者の姿勢制御に対する即時的効果
https://www.stroke-lab.com/speciality/20161
では日常生活への適用は?
運動強度の高いアスリートへの効果は期待できないにしても、日常生活者や何らかの障害を抱えている人へのサポートとしては一定の効果が認められているようです。
しかし、ざっと纏めると以下のような懸念点も指摘されています。
- 貼付け時に限った一時的な改善効果はあるが、治療を促進するような効果は見られない。
- 他の従来から有る方法の効果を、上回るものではない。
- 一見安価に思えるが使い捨てなので、継続的に使用するとなると経済的負担が大きい。
結局の所?
謳い文句通りでは無いと言え、一定の効果はあり経済性を除くデメリットも見当たりません。しかし、その理論を裏付けるエビデンスは無く、謳われている効果は過剰に見えます。
本当にそのまま製品のパッケージに書けば「健康増進法(誇大表示の禁止)」や 「景品表示法(優良誤認)」に当たりそうに思うのですが、実際には、販売を行わないポジション(推進協会や紹介サイト)で大きな効果を謳い、製品販売時には曖昧な表現に留められているように見えます。
スポーツや競技で実際に利用して良いと思っている人はそのままで良いと思います。「貼っている」という感触と、それからもたらされる心理的効果は、プラセボとは言え結果に有意な差は出ると思います。
あと、自分が指を痛めたままバイクに乗る時があって、知り合いに貼って貰ったことがあるんですが、その時はテープがちょうど指の動きを補助するような感じがして、主観としてはとても具合良く感じたことはあります。
先の引用例にもあったとおり、障害や傷病で弱っている部分の補助には良いのかも知れません。
ただ、個人的には、今後、積極的に使いたいとは思わないかなぁ。

さて、どうしようかなコレ。勢い余って通販でエラスティックテープと一緒にまとめ買いしちゃったよ…。まぁコレだけ買っても、ドラッグストアで買う値段の2本分以下だけど。