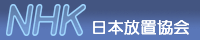今時の車のフロントガラスの上部を見ると、たいていカメラが付いてます。今話題のドライブレコーダー…では無くて、自動運転や運転支援のカメラ。
個人的には、なんだか内燃機関な自動車って、もっと電気より遠いメカメカしいイメージがあり、今時の電子制御てんこ盛りの自動車ってどうなん?ってちょっと引っかかってました。
キャブレターがインジェクション化したばかりの当時も「電気で制御されたインジェクションなんて…」と、凄く異質な物扱いされてましたし。
じゃぁ、昔の自動車は電気を使わなかったのか?電気を使わない自動車とは?って考えていくと「点火プラグ」で電気がどうしても必要というところに落ち着くわけで。
内燃機関の歴史
広義には花火のようなロケットとか往復運動の無いものも内燃機関に含まれるんですが、とりあえず今時のエンジン的な物に限ります。
歴史を遡ると、今のエンジンの原型?というか、最初の「実用的な内燃機関」と言われてるのがルノアールのガスエンジンで、それが1858年。
んで、電気の方がもうちょっと歴史が古くて、1700年代には既に静電気として、実用とはちょっと外れながらも利用されてました(エレキテルとか)。
「溜めたら放電して終わり」の静電気では無く、直流として安定的に利用できるようになったのはちょうど1800年の「ボルタの電堆(電池)」の発明以降のこと。
そして、そのルノアールのガスエンジンで使用されたのが電気点火方式で、この時初めて「電気式点火プラグ」として実用化されたわけです。エンジンだけでなく「点火プラグ」も一大発明だったわけで。
そんなわけで今のエンジンは電気と共に生まれてきたのであって、電子制御化していくのもわりと自然な事なんかな…という気がしないでもなく。
余談1)ルノアールのガスエンジンで使用された電気点火方式は「初めて実用化された電気点火方式」としては画期的だったようですが、予備圧縮を上げると点火不良を起こしたり、当時は既に他にも幾つかの点火方式が実用化されていたのですぐには普及しなかったようです(電圧が低かった?)。しかし、1902年のボッシュによる磁石とコイルを使った高電圧スパークの実用化以後は、電気点火以外の方式はほぼ淘汰されてしまったようです。
余談2)実はルノアールのガスエンジン以前にもレシプロ的なエンジンは既にありました。「大気圧ガスエンジン」と呼ばれるもので、ガス燃焼の圧力を動力として利用するのではなく、燃焼後のガスを密閉・冷却したときに出来る真空にかかる大気圧を動力として利用。1800年代初頭ではそれなりに稼働してたようです。